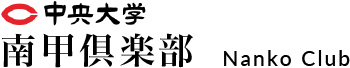企業交流委員会ではメンバー内の企業交流・業界研究の場を設け学んでいくことを企図し、各メンバーが持ち回りで自分の所属する会社や業界等をテーマに発表を行う情報交換会を行うことといたしました。2~3ヶ月に1回程度、定期的に実施していく予定です。
3月17日は第一弾として、『日本の建設業の歴史と海外進出』と題し、発起人である鈴木浩副委員長が講師を務め11名の参加で開催されました。自身のプロフィールに続き4項目の目次に沿って講義が進められました。

1)土地制度の歴史
飛鳥時代から現代に至るまでの土地制度の変遷を解説。朝廷の領地であった土地が武家・社寺の勢力に移り、江戸時代には幕府の直轄地へ。明治以降、地租改正や農地解放で土地の私有割合が増えたことなどを解説。また、日本では土地所有権の売買を認めるのに対し、海外では土地は国家が所有するため定期借地権のみが売買されるのが一般との説明がありました。
2)建設業の概要
日本の建設業経営が重層下請構造で“足し算で積算し、引き算で下請け発注する”ことによる利鞘から利益が生まれるのに対し、外国では施主と元請、元請と下請の関係を対等双務契約と位置付け、利益は生産活動の中で生まれる剰余(付加価値)と捉えているなど、日本と外国の考え方に大きな違いがあることを解説。
3)日本の建設業-歴史
江戸時代の官庁工事(普請奉行等による直営工事)や民間工事(発注者が材料支給、施工者は労務提供)から、幕末には各地の港建設等が始まり、施工を急ぐため一括請負方式を採用。海外から洋風建築技術が取り入れられ、技術者を擁する伝統的請負体制(設計施工)が確立。明治になると産業の発展、日清戦争など様々な時代背景から政府建設投資が増大し建設業が近代産業として成立。大正時代の関東大震災による耐震構造への認識。そして昭和になって戦後の混乱から自立する中、建設業界は欧米との技術格差克服のため各社が技術研究所を設立。以降、ゼネコンに設計・研究・技術開発部門が確立し、海外では他業種であるコンサルタントの領域をも併せ持つ、世界に誇れる日本のゼネコンが誕生したことなどを学びました。
4)日本建設業-海外進出
本格的な海外進出である戦後賠償ビジネスと、これに続く現地政府発注工事への挑戦・苦闘やその後の各社独自の海外展開などをゼネコン各社の具体的な海外実績などを含め解説。興味深かったのは、日本の建設会社が工期通りにものを造り上げ発注者に引き渡す「工事の完成」を目的としているのに対し、欧米の建設会社は契約書の権利・義務を履行するという「契約の履行」が目的であり、工事完成責任を契約者が一方的に負うものではないと捉え、自社の利益に合わない場合はターミネーター(清算人?)を送り込んで契約解除に持ち込む例もあるなど、彼我の違いを深く考えさせられる内容でした。
歴史や統計に関する調査・分析に加え、講師自身の建設業への深い関わりや豊富な海外赴任経験も反映しての私見も披露され、全く異なった業種の参加者も興味深く聴講できました。また、講義の合間々々にCoffee Breakとして関連情報が織り込まれるなど、オーディエンスを飽きさせない、にくい演出も施されておりました。

講義終了後は懇親会を開催し、さらにメンバー間の交流を深めたことは言うまでもありません。次回は「電鉄業界」を取り上げる予定となっています。
(企業交流委員会 野原正昭)